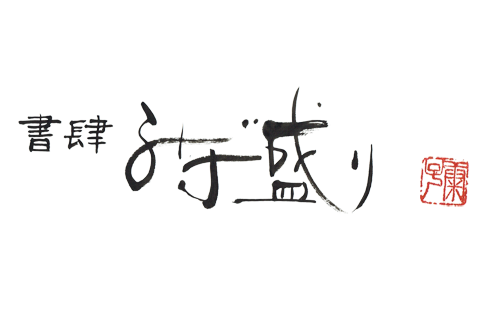伽鹿舎
佐藤亜紀
2017年12月23日初版第1刷発行 ライブラリー判・418頁 本体1,204円+税
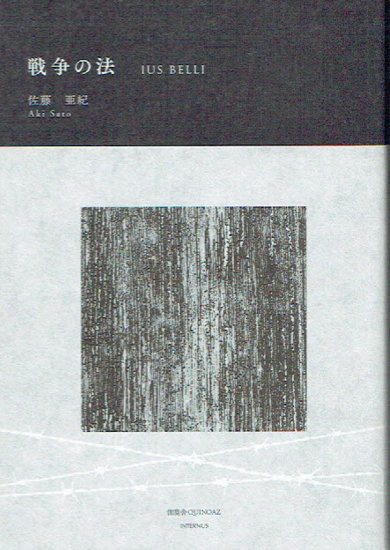
本当に存在しそうなリアリティと五里霧中の非存在感が
同居した世界観と、読めばわかる独特の文体と、
著者・佐藤亜紀らしさは充分すぎるぐらいに感じる作品だが、
舞台が日本なので読んでいるとしばしば、驚く。
驚くというか、びっくりするというか、
「あ、そうそう、佐藤亜紀読んでるんだった」という
不思議な感じというか。
舞台が日本になっただけでそう感じるということなのか、
本当はけっこう違う書き方をしているのか、よくわからない。
動乱の当事者というのは、それを目の当たりにした、
体験したという一点において後世の人間よりも
動乱自体に対して強い発言権を持つ。(変な言い方だが)
だが実際には、大きな騒ぎの渦中にいるひと一人の
感覚・感性が受け取れる情報量には限界があって、
できごとの全体を俯瞰して見る視点など持ち得ないし、
五感で得た貴重な情報にさえ主観のフィルターを通して
余分な、偏った観測を付け加えてしまうことも多い。
その、靄のかかったような、視野の限定された
もどかしさを抱えたまま疾走する臨場感と、
ことが終わった後に知り得た情報とを、
擦り合わせられればまだよかったのだろうが
それもできず、周りが見えていなかった自分自身への
羞恥とか落胆とか言い訳とか、そういうものまで
ごた混ぜにしてしまった見聞録のことを、
後世の研究者は一次資料と呼ぶ。
と断じてしまうと意地が悪いが、そう言いたくなるほど
本書の書かれ方は整然としているようで迷走しているし、
達観しているようだが言い訳がましい。
まさに一次資料、という感じがする。
これがフィクションなのだからびっくりする。
こういう経験を著者がしたわけではない、のは確かだ。
なにしろ、まだソビエト連邦があったころに、
新潟県(作中ではN***県と表現される)が
その傘下に入るような形で日本から独立する、
という筋立てである。現実な訳はない。
だが、そういう歴史事実があったかのようなリアルさで
本書は書かれていく。
その話を語る語り手は最序盤に、自らを
「信頼できない語り手」であると語る。
本来は叙述トリックの一分類としての言葉だが、
この場合の主人公を「信頼できない語り手」と
規定するのは間違っている。
もちろん、著者は狙ってやっているのだろう。
先述した、いかにも“一次資料”らしい
臨場感と言い訳の入り交じる読みづらさを、
主人公に間違った言葉でそれこそ“言い訳”させて、
この作品の本当らしさはさらに精度を高めた。
なんでこの作品が“鬼才の傑作”と評されていたのか、
読み終えてようやく見えた気がする。
こういう、CGでもどうにもできないような
凄みをはらんで疾走する作品は、
一番映画にできないのかもしれない。
感想というなら、凄いことするな、としか言えない。