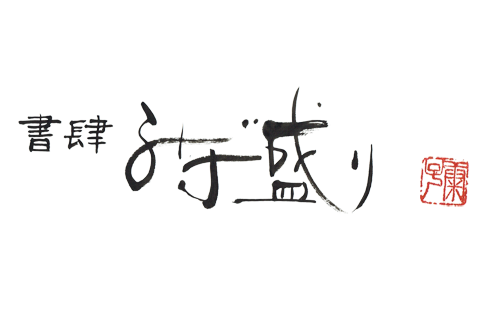立東舎
松崎順一
2016年4月25日 初版発行 A5判・176頁 本体1,800円+税

ラジカセ。
懐かしい言葉だ。
いまはもうポケットに入るカードのような機械で
音楽が聴けてしまう。
カセットテープなんかもう、見たこともない人も
だいぶ多くなっただろう。
テレビの音楽番組を録音したくて、
ラジカセをマイク録音状態にしてテレビの正面で
できるだけ効率的に音が入る位置に陣取りテープを回し、
余計な音を入れないように身動きにも気を遣っていたのに、
いいところで親父がデカい声でくしゃみをして
「うぉおおぉおおい!!!怒」と脱力する、などという
どこの家庭でもしばしば見られた悲劇も、
もう遠い記憶になった。
ちょっと近未来舞台の映画の台詞風にぼやいたが、
ラジカセにはそういう、ノスタルジックな良さがある。
CDラジカセに主役の座を奪われた時期、
大抵の機種は角が丸みを帯びたりポテっとして、
かっこ悪く感じたものである。
容易に持ち上がらない重さと大きさ、
うっかりぶつかれば凶器になりかねない四角さ。
機械はこうでなきゃ、といまでも感じるときがある。
メッシュカバーがかかったスピーカーはうっすらと
コーンの色が見えて、その見え方もまたデザインだった。
カセットデッキには残量確認のために小窓がつき、
ラジオチューナーもアナログで針がヌルヌルと左右に動く。
一つの機能に一つずつ割り当てられたメタリックなボタンの
配列と表示も、たぶんデザイナーの腕の見せ所だったろう。
液晶画面にプルダウンで現れるメニュー表示からは
得られない栄養が、物理ボタンにはあるのである。
ボタンや筐体がカラフルだったり、
形状が横長の四角柱に近かったり、
いろいろなパターンがあるのもまた面白い。
見た目だけでなく使い勝手、インターフェイスの部分まで、
画面の中のデジタルガジェットのような自由度が
持てないからこそ、ラジカセのような機械のつくりは
プロダクトデザインの象徴のひとつだったと思う。
まあこんな能書きを述べなくていいから、
一度ご覧なさい、お若いの。
見ているうちにぐっと愛着がわいてくるから。