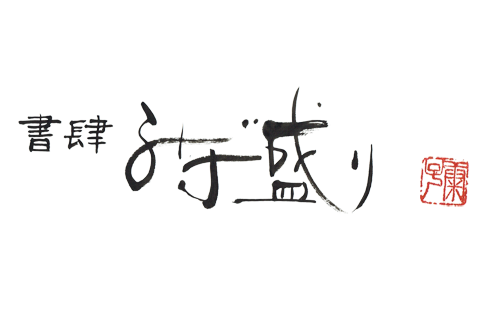夏葉社
三品輝起
2017年4月25日発行 四六判変形上製・288頁 本体2,000円+税
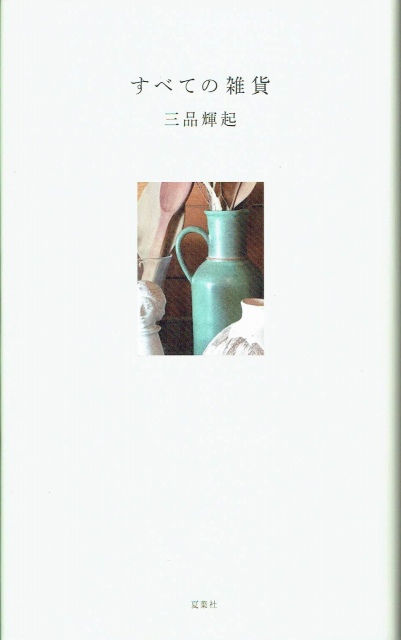
20年ほど前、雑貨店に連れて行かれた。
渋谷のスペイン坂の、いつも嗅ぎ慣れない香が焚かれ、
何時間かけても目が慣れそうにない色使いの商品が
いやというほど並べられている店だった。
置かれた商品と自分の感性とのギャップに苦しみ、
「コレカワイイネー」などと話しかけられても
「ソーダネー」と魂の抜けた声でしか返せない、
陽炎のようにゆがんで滲んだ記憶だけが残っている。
雑貨とはなにか。
思えば曖昧なその分類だが、著者の描く
「しかるに雑貨は、専門的な使いみちを
すこしでも放棄した物を見つけ次第、
どんどん自分たちの側に収奪していく。」
という表現がしっくりきた。
こまごまとした、それぞれ独立した物だったはずの ものたちは、
いつの間にか“雑貨という観念”にとりこまれ、
“雑貨というジャンルの中のなにものか”になりおおせる。
「もはやハサミだって金槌だってペンキだって、
製品の質だけでは測られない。かっこいいとか、
おもしろいとか、美しいとか、商品どうしをくらべたときの
イメージの落差にお金を払うのだ。…(中略)
たとえば文具や手芸用品なども用途だけ考えれば、
小学校の入学時点であらかたそろってしまう…(中略)
となりの席の友だちよりもかっこいい筆箱や、
クラスで一番かわいいハンカチをもつことが
競技種目としてせりだしてくる。」
なるほど。
普段、差別化などと呼んで売り文句にしているその差異が、
純粋に道具だったはずの物を雑貨化していく。
住宅の世界も、システムキッチン、ユニットバス、
造り付けの家具に建具、照明器具などなど、売る側の人間が
どんどん雑貨化させてしまっている現状に気付いて慄然とした。
「百円ショップを利用して部屋をカリフォルニアスタイルにしよう、
みたいな難解な本も残念ながら書けない。」
著者の皮肉を笑えたのは一瞬だけで、
浮かんだ笑いはすぐ消えてしまった。
スペイン坂の雑貨屋で、彼女はなにも買わなかった。
私には、欲しい物がなにもない店だった。
何を見てそう感じたのか。
では欲しい物がなんなのか、と問われれば、
いまも即答はできない。